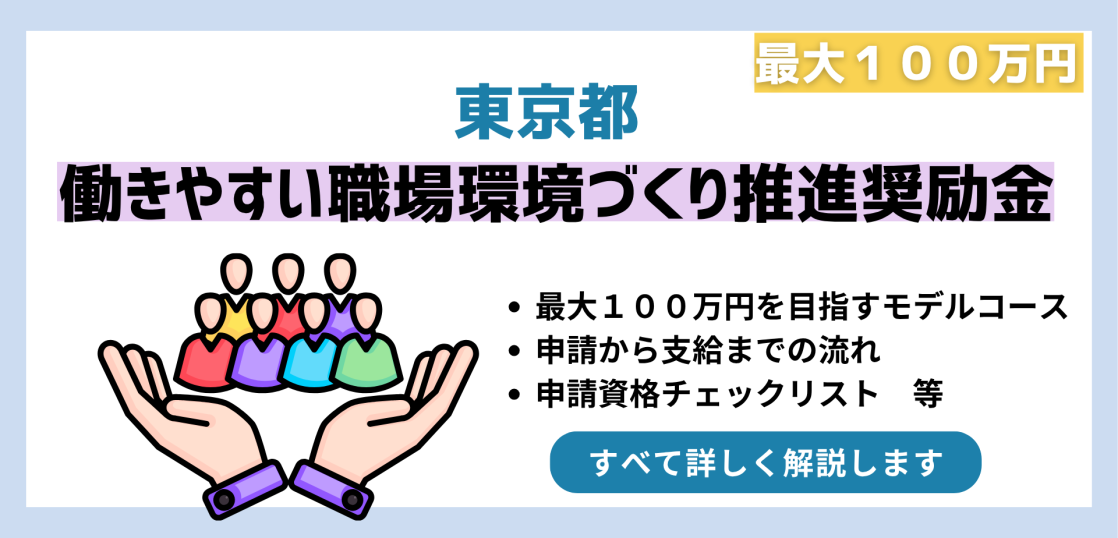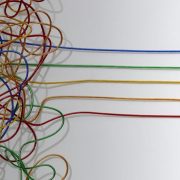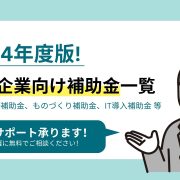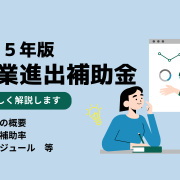目次
「従業員のライフイベントと仕事の両立を支援したいが、何から手をつければ…」
「人材の定着と確保のために、もっと働きやすい環境を整えたい」
こうした課題を抱える東京都内の中小企業を力強く支援するのが、東京都の「働きやすい職場環境づくり推進奨励金」です。
この制度は、育児・介護・病気治療と仕事の両立支援に取り組む企業に対し、コースに応じて定額20万円または40万円、合計で最大100万円の奨励金を支給するものです 。
本記事では、公式サイトの情報のみに基づき、この魅力的な奨励金の仕組み、対象となる取り組み、そして申請から受給までの全ステップを、専門家の視点から徹底的に解説します。
「働きやすい職場環境づくり推進奨励金」とは?
本奨励金は、都内の中小企業が従業員の「仕事と私生活の両立」を支援するための具体的な社内制度を新たに整備・導入する取り組みを経済的に支援する制度です。
目的は、育児、介護、病気治療といったライフステージの変化に直面した従業員が、キャリアを中断することなく働き続けられる環境を構築することにあります。
これにより、企業は従業員のエンゲージメント向上と離職防止を図ることができます。
奨励金額:コース選択と組み合わせで最大100万円
奨励金は、企業の課題に応じて選択・組み合わせが可能な複数のコースから構成されています。
支給額は、各コースで定められた取り組みを完了したことに対して支払われる「定額」です 。
| コース分類 | 主なコース内容 | 奨励金額 |
| A:育児と仕事の両立 | A① 育児関連の休暇制度整備 A② 男性の育児参加推進 など | 20万円 |
| A③ 育児中のための多様な働き方整備(短時間勤務、在宅勤務など) | 40万円 | |
| B:介護と仕事の両立 | B① 介護と仕事の両立推進事業(相談窓口設置+計画策定) B② 介護離職防止のための制度整備事業(法定を上回る介護休業制度の新設など) | 各40万円 |
| C:病気治療と仕事の両立 | 治療のための休暇制度や柔軟な勤務制度の新設など | 20万円 |
| 追加取組 | 経営者・管理職向け研修の実施、ジョブリターン制度の整備など | 各20万円 |
★Bコースは2段階構成
・B① 介護と仕事の両立推進事業 40万円(相談窓口設置+計画策定)
・B② 介護離職防止のための制度整備事業 40万円(B①を実施した企業が追加で実施可能)
★体験型研修(+20万円)はAコースまたはBコースのいずれかを実施した企業のみが対象です(Cコース単独の場合は加算不可) 。
★ジョブリターン制度(+20万円)は A①・A③・B②・Cのいずれかを実施した場合のみ加算できます(A②・B①単独では不可)
これらのコースや追加取組を戦略的に組み合わせることで、1企業あたり合計で最大100万円の奨励金を目指すことが可能です 。
モデルケース:最大100万円を目指す組み合わせは?
これらのコースや追加取組を戦略的に組み合わせることで、1企業あたり合計で最大100万円の奨励金を目指すことが可能です。いくつかモデルケースを見てみましょう。
《モデルケース1:育児支援を重点的に行うパターン》
- A③ 多様な働き方整備(40万円)
- + A② 男性の育児参加推進(20万円)
- + 経営者・管理職向け研修(20万円)
- + ジョブリターン制度(20万円)
- 合計:100万円
《モデルケース2:介護離職防止に特化するパターン》
- B① 介護と仕事の両立推進事業(40万円)
- + B② 介護離職防止のための制度整備(40万円)
- + 経営者・管理職向け研修(20万円)
- 合計:100万円
【最重要】この奨励金のゴールは「制度の導入」です!
この奨励金を申請する上で、絶対に知っておくべき最も重要なルールがあります。
それは、この制度がかかった費用を後から精算する「経費補助」ではない、という点です。
東京都が見ているのは「eラーニングにいくら払ったか」という領収書ではありません。
そうではなく、「会社に新しい両立支援の仕組み(制度)が正しく導入されたか」という事実に対して、決まった額がご褒美として支払われる「定額奨励金」なのです。
では、「制度の導入」とは、具体的に何をすればゴールと見なされるのでしょうか?
それは主に、以下の3つのアクションを完了させることを指します。
アクション①:ルールを作る(就業規則への規定)
新しく作る休暇制度や勤務制度の内容を、会社の公式ルールブックである「就業規則」にきちんと明記します。これが制度を作ったという何よりの「証拠」になります。
アクション②:社内に知らせる(従業員への周知)
「こんな制度ができました!」ということを、社内説明会や掲示物、メールなどで全従業員(パート・アルバイト等も含む)に知らせます。
アクション③:使える状態にする(運用体制の整備)
実際に従業員がその制度を使えるように、相談窓口の担当者を決めたり、休暇の申請書フォーマットを用意したりします。
【よくある質問】この取り組みは対象になりますか?
この3つのアクションをふまえて、ご要望の多いキーワードがどのように扱われるか、Q&A形式で解説します。
Q1.「病気治療と仕事の両立相談窓口」の設置は対象ですか?
A1. はい、Cコース(病気治療支援)の中心的な取り組みです。社内に相談窓口を設置し、担当者を決め、そのことを従業員に知らせる(アクション②③)ことで、コースの要件を満たします。
Q2. 制度を知らせるために「メンタルヘルスeラーニング」を導入したいのですが。
A2. eラーニングの購入費用そのものが補助されるわけではありません。しかし、新設した相談窓口の使い方やメンタルヘルスケアの重要性を周知するためにeラーニング研修を行うことは、「アクション②:社内に知らせる」の一環として有効です。奨励金は、この活動を含めて「制度がきちんと導入された」と認められた結果として支払われます。
Q3. 従業員の健康のために「運動イベント」は対象になりますか?
A3. 従業員の健康を思う素晴らしい取り組みですが、この奨励金の目的である「育児・介護・病気治療との両立支援」とは少し異なります。もし運動イベントや社内サークル活動への支援をご希望の場合は、東京都の別の制度『魅力ある職場づくり推進奨励金』が合致する可能性が高いです。自社の目的に合った制度を選ぶことが重要です。
4. 申請から支給までの流れと「3つの黄金律」
申請プロセスは複数のステップから成り、それぞれに厳格なルールが存在します。
| ステップ | 主なアクション |
| 1. 事前エントリー | 「TOKYOはたらくネット」からオンラインでエントリー。受付期間が非常に短く、応募多数の場合は抽選となります 。 |
| 2. 交付申請 | 抽選に当選後、事業計画書など正式な申請書類を提出します。 |
| 3. 交付決定 | 審査を経て「交付決定通知書」が送付されます。 |
| 4. 事業実施 | 交付決定後、3ヶ月以内に計画した取り組み(制度の就業規則への規定、研修、周知など)をすべて実施します。 ・★都内勤務従業員(パート含む)を対象に社内説明会を開催し、出席率50%以上を達成することが必須要件です(複数回開催・オンライン併用可) 。 |
| 5. 実績報告と受給 | 事業完了後、実績報告書を提出。審査を経て奨励金が振り込まれます。 |
このプロセスにおいて、絶対に守るべき「3つの黄金律」があります。
・黄金律①:都が指定するオンライン研修参加が前提
交付申請後、事業実施に進むためには、東京都が指定するオンライン研修の受講が必須です。この研修では、制度設計のポイントや提出書類の注意点などが解説されます。
・黄金律②:計画→交付決定後に経費発生可能
奨励金の対象となるのは、「交付決定通知書」を受け取った日以降に契約・発注・着手した取り組みのみです。交付決定前にコンサルタントと契約したり、研修を申し込んだりした場合、その経費はすべて対象外となってしまいます。
・黄金律③:社内説明会の参加率5割以上が必須
事業実施のフェーズで、都内勤務の全従業員(パート、アルバイト等を含む)の5割以上が参加する社内説明会を開催することが絶対条件です。この要件を満たせない場合、他の取り組みをすべて完了していても奨励金は支給されません。
5. 申請資格セルフチェックリスト
自社が申請資格を満たしているか、以下のリストでご確認ください。
| 要件 | チェック |
| 都内に本社または事業所がある中小企業(常時雇用する労働者300人以下)ですか? | □ |
| 都内勤務の常時雇用労働者が2名以上いますか?(うち1名は6ヶ月以上継続雇用) | □ |
| 【最重要】就業規則を作成し、労働基準監督署へ届出済みですか?(従業員10人未満でも必須) | □ |
| 労働関係法令を遵守し、都税の未納がありませんか? | □ |
まとめ
東京都の「働きやすい職場環境づくり推進奨励金」は、最大100万円という直接的な経済的メリットに加え、従業員の満足度を高め企業の社会的評価を向上させるという大きな価値をもたらす制度です。
ポイント
- 育児・介護・病気治療との両立支援制度の導入で、コース定額20万円or40万円、合計上限100万円の奨励金。
- メンタルヘルスeラーニングや病気治療と仕事両立の相談窓口設置といった取り組みに活用可能。
- 都が指定するオンライン研修参加が前提であり、計画→交付決定後に経費発生可能というルールは厳守。
- 運動イベント等は、別の「魅力ある職場づくり推進奨励金」の対象となる可能性あり。
申請の第一歩は、非常に短い期間で締め切られる「事前エントリー」です。
まずは「TOKYOはたらくネット」で次回の募集スケジュールを確認し、計画的に準備を進めることをお勧めします。
令和7年度東京都働きやすい職場環境づくり推進奨励金のご案内:
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/koyoukankyo/files/260e15c38a13f471585f80890946d3a3.pdf