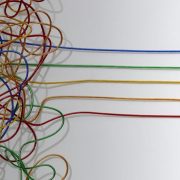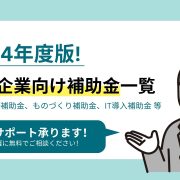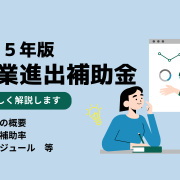大規模成長投資補助金
省力化や労働生産性の向上、人手不足の解消といった効果が複数拠点で一体的に発揮され、事業として整合性・一貫性があればまとめて申請いただけます。
新たに提出された計画のみで審査しますので、1次公募の結果や内容は考慮しません。
はい。プレゼンテーション審査では代表権をもつ経営者(社長等)のプレゼンが必須要件となります。
それぞれの公募ごとに最新の様式が公開されますので、必ず最新様式をご利用ください。
やむを得ない事情がある場合は速やかに事務局へご連絡ください。別日程への調整が可能か個別にご案内します。
今後の予算や執行状況を踏まえて検討される可能性がありますが、現時点では未定です。
jGrantsポータルサイトの「申請の流れ」ページに操作マニュアルが掲載されていますので、ご参照ください。
大企業も投資に参加し賃上げ要件を満たす場合は参加自体は可能ですが、大企業分の投資は補助金の交付対象外となります。
原則、最終的に稼働可能な状態に至っていないと補助対象経費と認められないため、途中段階のみで完了しない場合は対象外となる可能性があります。
事業拡大に関連する資産(有形・無形)への投資が補助対象になります。具体的には、建物費、機械装置費、ソフトウェア費、外注費、専門家経費などが含まれます。nソース: 『公募要領_2ji.pdf』p.10
①賃上げ目標未達成、②補助事業の中止・廃止、③補助対象経費の誤用、④実地検査による指摘 などが発生した場合、補助金の返還が求められます。nソース: 『補助事業の手引き(2次公募).pdf』p.46
該当年度で12か月分の給与を受けた常時使用従業員は全て算定対象に含めます。パート社員などは正社員の就業時間に換算して人数を算出してください。
公道を走行する車両(自動車等)以外で、専ら事業に使用される設備であれば補助対象となり得ます。実際の資産区分や使用目的については税理士や申請書類で確認されます。
1次審査(書面審査)通過後に個別に日時を連絡します。全体の実施期間はホームページ等でも案内予定です。
共同申請(コンソーシアム形式)を利用できます。補助事業に要する経費が実際に発生する参加者のみ含める点など、公募要領の要件をご確認ください。
専ら補助事業のために利用するサイトの開設・運用・保守経費であれば対象です。ただし期間が補助事業期間中のみであること、他事業と共用しないことなどに注意してください。
事業にかかる自社の人件費(ソフトウェア開発等)は補助対象外です。nソース: 『公募要領_2ji.pdf』p.14
他の補助金と併用することは可能ですが、同一経費に対して複数の補助金を受ける「二重取り」は禁止されています。nソース: 『補助事業の手引き(2次公募).pdf』p.48
同一設備・同一経費に対する国の補助金との重複は認められませんが、自治体補助金や一部の税制優遇と併用できる場合もあります。
発注目的ではなく見積取得や検討依頼などの意味合いならば発注とみなされません。ただし実質的に契約を確定する行為であれば発注扱いとなり、補助対象外になります。
jGrants上では「申請済」「差戻」などのステータスのみ確認可能です。採択結果はメール通知および特設サイト上で公表されます。
採択後の交付申請時に変更希望を申請いただけます。ただし、新規追加の経費や補助額の増額はできず、計画の大幅変更は承認されない可能性がある点にご注意ください。
申請時点では提出不要ですが、機械装置や建物の単価・個数を把握したうえで成長投資計画を作成してください。採択後に交付申請をする際には、有効期限内の見積書が必要となります。
コンソーシアム全体として1件の申請とみなすため、全体で最大50億円です。
各社ごとに収入・支出を記載し、合計が補助事業全体の計画と一致するようにしてください。
補助事業により取得した財産の種類(建物、機械装置など)によって異なり、該当する耐用年数の期間が処分制限期間となります。
総合特区・復興特区による利子補給との併用は可能です。ただし他の国の補助金による二重受給にはご注意ください。
同一の公募期間内での複数申請はできませんが、前回公募で不採択となった場合は次回公募に再申請することは可能です。ただし既に採択され交付決定を受けた事業者は再申請できません。
補助対象外です。
税制優遇の適用が「まだ確定していない」段階であれば、本事業に申請しても差し支えありません。適用が確定した設備については重複対象外となります。
地域未来投資促進税制の法人税等の優遇との重複は不可ですが、自治体による不動産取得税や固定資産税の減免は併用可能です。
地域の雇用を支える中堅・中小企業が、足元の人手不足等の課題に対応し、成長していくことを目指して行う大規模投資を促進することで、地方における持続的な賃上げを実現することを目的とした制度です。
成長投資計画(様式1)で、省力化や労働生産性向上・売上拡大などの具体策が人手不足の解消につながることを数値や根拠を交えて示していただきます。
一般管理費と現場管理費は補助対象外です。
建物の改修として、賃上げや労働生産性向上に資する投資計画であれば対象となり得ます。
事業者の資産計上方法に準拠して区分した各建物費が100万円以上であるかを基準としてください。
塀や門扉、舗装、防油堤、砂利道、遮へい壁等が挙げられます。実際の資産区分が建物か構築物かは税理士など専門家へご確認ください。
見積書を取得できない理由と価格妥当性を示す書類を交付申請時に提出してください。相見積もりが難しい特段の理由が必要です。
採択や交付決定の前に契約・発注していた経費は原則対象外となります。したがって、事業自体が採択前に始まっていても、交付決定前に結んだ契約分は補助に含められません。
業種ごとの優遇はありませんが、賃上げの実現可能性、成長戦略の明確性、大規模投資の適切性、早期の事業実施 などが評価されます。
補助対象となる設備投資額が10億円を下回ると要件不達となるため交付決定はできず、交付決定後であれば取消となります。
採用は原則自社で行える業務とみなされるため、外注費としては認められません。
同一設備に対し、政府系金融機関の融資と本補助金を併用すること自体は問題ありません。詳細は各金融機関へご相談ください。
事業部門ごと、または会社全体などの単位で設定いただきます。どの範囲の従業員を賃上げ対象にするかによって適用する都道府県の基準値が変わります。
FITやFIPなど公的制度を利用する売電目的の設備は対象外ですが、それらを用いない自己消費や事業効率化目的での発電設備であれば、本事業の趣旨に合致する限り補助対象となり得ます。
公募申請時点で確定決算がない場合は、基準年度を「補助事業完了日が属する年度の翌事業年度」とすることができます。
交付決定前に支払った経費は補助対象外です。補助対象となるのは、交付決定後に契約・発注・支払いが行われたものに限られます。nソース: 『補助事業の手引き(2次公募).pdf』p.26
原則、補助事業を主とする事業部門を最小単位として従業員数と給与支給総額を算定します。ただし、事業部門ごとの区分が難しい場合や会社全体として賃上げを行う場合などは、会社全体の従業員数・給与支給総額を用いても構いません。
自社保有の設備を単に移設する費用は補助対象外です。
昇給・減給など給与変動があっても、基準年度や各年度で全期間の給与支給を受けた従業員であれば賃上げ算定対象に含めます。
事業規模拡大や賃上げに結びつく投資であれば対象となり得ますが、単なる施設整備だけでは補助対象として認められない場合があります。
共同申請(コンソーシアム形式)での一体的な投資計画であれば可能です。ただし要件(投資額や賃上げなど)を満たしていることが必要です。
追加担保差入条項が存在し実質的に補助事業の建物が担保に含まれる場合は対象外です。金融機関の同意を得て建物部分への根抵当を外すなどの手続きが必要です。
必要事項が網羅され審査に支障がない限り、ある程度アレンジしていただいて構いません。
うるう日はシート上で計算反映が難しい場合があるため、便宜上2月末日として入力するなど調整をお願いします。
貸借対照表項目は決算書通り、損益計算書項目は12か月換算で記入し、その計算根拠を添付してください。
事業者の仕訳上で電子記録債権・債務を手形として処理している場合は含めて問題ありません。
押印は不要です。
内容が判別しやすいよう「決算書(前期)」「決算書(最新期)」など、資料名と対象期間、会社名を入れたファイル名にしてください。
派遣社員は派遣元から給与が支払われるため含みません。技能実習生は貴社が直接給与を支払う常時使用従業員であれば含まれます。
補助事業で専ら使用する機械・設備ならば、輸送費や据付費用も一体の投資として認められる場合があります。
そのドライバーが常時使用の従業員(直接給与を支払われる従業員)であれば賃上げ対象に含みます。
公募締切後にまとめて審査しますので、申請の早さは採否には影響しません。ただし締切直前はシステムが混み合う可能性が高いため、余裕を持った提出をおすすめします。
期日内であれば、事務局にご連絡いただき不備箇所を明示のうえ再提出してください。
交付申請時に提出が必要な書類は、①交付申請書、②成長投資計画書、③成長投資計画書別紙(経費明細など)、④見積書(相見積を含む)、⑤会社の決算書(3期分)などです。nソース: 『公募要領_2ji.pdf』p.20
達成率に応じた返還を想定しています。具体的な計算方法や返還手続きの詳細は「補助事業の手引き」で別途案内予定です。
期限後の提出はどのような理由でも認められません。必ず締切までに全ての書類を揃えてください。
申請書類のフォーマットは指定されており、公式サイトからダウンロードできます。また、ファイル名の命名規則にも注意が必要です。nソース: 『公募要領_2ji.pdf』p.21
公募締切の数営業日前までに提出いただいたものは不備があれば再提出可能ですが、締切直前は時間的に余裕がなくなる場合があるため、お早めの申請をおすすめします。
はい、申請は電子申請システム(jGrants2.0)を通じてオンラインでのみ受け付けられます。nソース: 『公募要領_2ji.pdf』p.17
書類の不備や不足を事前に確認し、申請前に見直すこと(不備があると審査対象外になる可能性あり)。ファイルサイズは10MB以下にし、命名規則を遵守すること。補助金の目的に合致した内容を記載すること。
3次公募の申請期間は未定ですが、3月頃と言われています。
主要な活動(売上高や利益が最大の事業)を基準にしつつ、一体的な投資計画であればまとめて申請することは可能です。
給与所得として課税されない経費は含まれないため、福利厚生費・賞与引当金・通勤費は賃上げ算定の給与支給総額に含めません。
国からの補助金との二重受給にならなければ可能です。
自社内製品やグループ内取引は補助対象外です。また部品の購入費は「目的外使用可能なもの」とみなされる場合が多く、対象になりにくいです。
当該従業員は退職した年度以降は算定対象から外れます。基準年度および途中年度で全月勤務していない場合は計算に含めません。
例えば農作物の生産(1次産業そのもの)を主とする事業は対象外ですが、2次・3次産業に該当する取り組みであれば補助対象となり得ます。また、公序良俗に反する事業や法令に違反する事業は対象外です。
「1人当たり給与支給総額」の年平均上昇率で計算します。従業員数の増減は総支給額と人数で割り算し、1人当たり額として比較します。
補助事業実施場所の都道府県の給与平均上昇率を用いて賃上げ基準を定める必要があるため、公募申請時点で実施場所を確定いただく必要があります。
賃上げ率の計算には、各年度で全月分(12か月分)の給与を支給された従業員だけを含めるため、中途入社の従業員は翌年度以降に計上します。
原則は補助事業の従業員を対象としますが、区分が難しい場合は会社全体など広い範囲で算定してもかまいません。
リース資産の所有権はリース会社にあるため、倒産時にはリース会社が補助金相当分の処分手続きを行う必要があります。
原則として補助対象資産が抵当に入ることは認められません。工場財団として一括設定される場合、補助事業で取得した資産が追加担保とみなされるなら対象外となります。
補助率は1/3ですが、上限額があるため最大50億円となります。
原則、クレジットカード払いは認めておりません。
①経営力、②成長戦略、③大規模投資・費用対効果、④実現可能性 の4つの観点で評価されます。長期成長ビジョン、競争優位性、費用対効果、投資計画の妥当性などが審査基準となります。
概算払いと精算払いの2回に分けて受け取ることが可能 です。交付決定後に一定割合を先払い(概算払い)し、補助事業完了後に残額を受け取ります。最大6回の概算払い請求が可能です。nソース: 『概算払請求時にご確認いただきたいポイント(2次公募).pdf』p.6
指定口座への銀行振込となります。
通常、補助金に返済義務はありません。ただし、補助金の条件を満たさない場合(賃上げ未達成、不正受給、事業廃止等)には返還義務が発生します。nソース: 『補助事業の手引き(2次公募).pdf』p.46
補助金は課税対象 となります。補助金を受けた年度の収入として計上し、法人税・所得税の課税対象となります。固定資産取得に充てる場合は、圧縮記帳が可能です。nソース: 『よくある質問一覧_交付申請以降_Ver8.0.pdf』p.9
法人の場合は法人名義の口座、個人事業主の場合は事業主名義の口座が必要 です。通帳の表紙と取引明細のコピーの提出が必要です。nソース: 『補助事業の手引き(2次公募).pdf』p.33
採択後は、①交付申請、②交付決定後の補助事業実施、③実績報告、④事業完了後のフォローアップ(3年間の報告義務、監査)などが求められます。
はい、GビズIDプライムアカウントの取得が必須 です。未取得の場合、申請できませんので事前に取得する必要があります。
補助率1/3以内(上限50億円)の範囲であれば、補助金額を低めに設定して申請することも可能です。
50億円・1/3です
同一グループ内に50%以上の議決権保有がある場合は同一法人とみなし、別々の申請はできません。共同申請(コンソーシアム形式)での申請をご検討ください。
設備投資(建物・機械装置等)や、専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築費用は補助対象に含まれます。ただし、パソコンやタブレット端末本体は対象外です。nソース: 『補助事業の手引き(2次公募).pdf』p.50
倉庫業として事業を拡大し、労働生産性向上などの効果が見込まれる投資であれば対象となり得ます。
原則、補助事業を実施する場所の都道府県の基準値を用います。補助事業に関わる従業員・役員をどの範囲で対象にするかによって変動します。